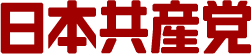○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
政府は、二月十八日、第七次エネルギー基本計画と地球温暖化対策計画を閣議決定いたしました。温対計画では、国連に提出する二〇三五年の国別削減目標、NDCが示されましたが、その内容は、二〇一三年比六〇%削減、IPCCの基準年、二〇一九年比では五四%程度の削減となり、昨年十二月、当委員会で私が指摘したとおり、経団連が提言した削減目標と同じものとなりました。
この計画を議論した審議会あるいはパブコメで、多くの若い世代や市民、環境団体が、IPCCが示した一・五度目標に必要な削減基準、二〇一九年比六〇%削減から見て極めて低いとか、先進国として責任ある目標となっていないとか、石炭火力をやめようとせず、若い世代の未来を守ることができないとの批判の声を上げていたにもかかわらず、その声に応えるものとはなりませんでした。
浅尾環境大臣、新しいNDCは、地球の未来、若者の未来より、経団連の利益、要求を優先したということではありませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 新たなNDCについては、環境省、経済産業省の合同審議会において、専門分野、年齢層、性別等のバランスにも留意しつつ、若い世代にも委員として参画いただき、審議を行いました。また、若者団体含む様々な主体からのヒアリングの結果も踏まえながら検討を進めてまいりました。その中では、政府案としてお示しした直線的な経路を支持する御意見、経済に与える負の影響を踏まえ削減目標を低く設定すべきといった御意見、先進国としてより野心的な目標を設定すべきといった様々な御意見をいただきました。また、これらの御意見を示しつつ、パブリックコメントを実施し、その結果も踏まえ閣議決定に至ったものであります。
このように、経団連を含む産業界の意見のみを優先したという事実はございませんが、引き続き、若い世代を始め多様な御意見等を丁寧に伺いながら気候変動対策を進めてまいりたいと考えております。
○山下芳生君 若い世代はそうは思っていないんですよね。いっぱい声上げたと。審議会にも入った人もいます。しかし、せっかく出した意見が反映されなかったと。結局、経団連の意見が採用されたというのが、若い世代、環境団体などの実感なんですね。
一月十日、世界気象機関、WMOは、二〇二四年の世界の平均気温の上昇が産業革命前の水準と比べて一・五五度上回ったと発表しました。パリ協定で気温上昇を抑える目標とされる一・五度を単年で初めて超えました。世界の平均気温の上昇は科学者の予測を上回っております。私も驚きました。
既に、世界でも日本でも、巨大台風、豪雨災害が頻発し、大規模な山火事が多発しております。日本でも起こりました。今現在どのような対策を取るかが、今後長期にわたって、若い世代の存続、人類の生存にも大きな影響を与えていくことになります。繰り返し言いますけれども、温室効果ガスを早期に大量に削減する、化石燃料から脱却する、その道筋をつくることが先進国である日本の世界に対する責任、将来世代に対する責任であります。一部の大企業の目先の利益を優先することは決して許されないというふうに思います。
気候危機がこうして深刻化する中、アメリカのトランプ政権がパリ協定からの離脱を表明しました。世界が協力して取り組むべき人類的課題に排出量第二位の国が背を向けるという極めてゆゆしき態度であり、世界から非難されております。ところが、石破首相は、二月八日の日米首脳会談でこの問題に一言も触れませんでした。浅尾環境大臣は、首脳会談前に石破首相からこの問題について相談を受けたのでしょうか。あるいは、事前にこの問題に触れませんよということを知らされていたのでしょうか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 日米両国そして国際社会が直面する課題は実に多く、先般行われた日米首脳会談ではそれらの全てを取り上げる時間はなかったと承知をしております。
いずれにせよ、気候変動は人類共通の待ったなしの課題であり、主要排出国を含む全ての国の取組が重要であることに変わりはありません。世界の気候変動対策への米国の関与は引き続き重要であり、州政府や産業界含めた米国と協力していく方法を探求してまいります。
○山下芳生君 質問は、石破さんがアメリカに行く前に浅尾さんに相談したのかということなんです。どうですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 政府部内における調整過程についてつまびらかにすることは差し控えたいと思います。
今後も、しっかりと日米間でも話をしていきたいというふうに考えております。
○山下芳生君 何か進言しました、石破さんに。進言。この問題はこうした方がいいですよというのは。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今申し上げたとおりで、政府内の調整についてはつまびらかにすることは差し控えたいと思います。
○山下芳生君 いずれにせよ、結果は、浅尾環境大臣がどのようにコミットしたかは知りませんが、一言も言わなかったわけですね。
私は、真の友人というのは、自分が間違ったことをしたときに、あなたそれは間違っているよと言ってくれる人が真の友人だと思うんですよね。まして人類の生存が懸かった問題での間違いは、言わなかったら、触れなかったら、触れなかった側の責任が問われることになると、そう思います。
ですから、私は、浅尾大臣が、日米首脳会談では米国のパリ協定離脱問題について首脳会談にふさわしい形で、あなた方はもう地球の敵だみたいなことを言う必要ないと思いますよ、でも世界は危惧していますよと、心配していますよと我々も、ふさわしい形で言うことはできたはずなんですよ。で、そのことを環境大臣の職責を懸けて私は総理大臣に進言するのが浅尾さんの役割だと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほどの答弁と繰り返しとなりますけれども、政府部内における調整過程についてはつまびらかにすることは差し控えたいというふうに思います。
○山下芳生君 それは分かったんですけど、こういう問題はちゃんと言うべきことは言うべきだと、環境大臣として総理に、その辺はいかがですか。それがあなたの職責ではないですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 繰り返しになる部分もあるかもしれませんが、世界の気候変動対策への米国の関与は引き続き重要であると考えております。
トランプ大統領が、パリ協定から脱退について署名した大統領令において、米国は、これまで経済成長と同時に温室効果ガスの排出を削減してきたこと、また環境保護のための世界的な取組においてリーダーシップを果たすことを表明しており、連邦政府の今後の政策の動向を注視してまいりたいと。
我が国としては、これまでも国レベルだけではなくてカリフォルニア州との協力なども行っておりまして、今後様々な機会で米国の関係者と話をし、州政府や産業界も含め米国と協力していく方法を探求していきたいと考えております。
○山下芳生君 大変情けない答弁しか返ってこなかったなと率直に言って思います。
だって、さっき言ったように、産業革命前から一・五五度上昇したわけですよ、世界の平均気温が。もうティッピングポイントをいろんな面で超えたかもしれない、もう取り返しの付かないことが起こっているかもしれないときに、世界第二位の排出大国がその枠組みから抜け出しますということを言った直後の日米首脳会談ですよ。言わなきゃ。あれこれのいろんな問題、もちろんありますけれども、これを避けて言うような軽い問題ではないですよ。第一級の人類史的課題を触れなかったというのは、私は環境大臣が閣内でどういう役割を果たしたかは分かりませんけれども、結果として役割を果たせなかったということを強く指摘しておきたいと思います。
それからついでに言っておきますと、言うべきことを言わなかっただけではありません。会談で両首脳は、対日貿易赤字の穴埋めのために米国から日本への液化天然ガス、LNGの輸出拡大で合意をいたしました。パリ協定から離脱を表明し気候危機打開に背を向けているアメリカから化石燃料、LNGを買って協力するのは世界の流れにいよいよ逆行しているということも一言言っておきたいと思います。
そういう中で、米国の離脱表明で世界の脱炭素の取組の遅れが危惧されるんですが、排出量世界第五位の日本が一定量をカバーする高い削減目標を持って積極的に貢献することが私は期待されると思いますが、この点はいかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 気候変動は人類共通の待ったなしの課題であり、主要排出国を含む全ての国の取組が重要であることに変わりはありません。また、脱炭素の取組は現在の世界的な潮流になっていると考えております。
我が国としては、先月閣議決定した地球温暖化対策計画などに基づき、二〇五〇年ネットゼロに向け脱炭素と経済成長の同時実現を目指し、揺らぐことなく気候変動対策に取り組んでいくことが重要であると考えております。また、国際社会に対しても、このような我が国の考え方を様々な機会を通じてしっかりと説明してまいります。
○山下芳生君 揺らぐことなく気候変動対策に取り組むのだということですが、ちょっと心配なことが私はあるんですね。
資料一に、資源エネルギー庁のエネルギー基本計画の概要から、参考、二〇四〇年における新たなエネルギー需給見通しを添付いたしました。赤線引いたところにあるんですけれども、参考、新たなエネルギー需給見通しでは二〇四〇年度七三%削減実現に至る場合に加え実現に至らないシナリオ、六一%削減も参考値として提示とあります。
今日は経済産業省にも出席いただいておりますが、この実現に至らないシナリオ、いわゆるリスクシナリオとは何ですか。リスクシナリオを作成した理由は何ですか。これまで作成したことはありますか。御説明いただけますか。
○政府参考人(木原晋一君) お答え申し上げます。
二〇四〇年度のエネルギー需給見通しでは、二〇四〇年度温室効果ガス七三%削減、二〇五〇年カーボンニュートラルを前提に、再エネ、水素など、CCSなどの分野において技術革新が実現することを想定した上で、将来のエネルギー需給の姿を一定の幅でお示ししております。
御指摘のいわゆるリスクシナリオは、それとは別に、二〇五〇年カーボンニュートラル実現に向けて更なるイノベーションが不可欠であるところ、二〇四〇年度時点において脱炭素技術の開発が期待されたほど進展せず、コスト低減等が十分に進まないような事態にもエネルギーの安定供給を確保するべく、参考値としての技術進展シナリオをお示ししたものでございます。
政府としては、こういう場合にも必要な政策手段を準備しておくことが責任あるエネルギー政策のためには必要であると考えております。経済成長を実現しながら、国民生活をエネルギー制約から守り抜くために、LNGの長期契約の確保を含め、エネルギー安定供給の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 要するに、閣議決定し国連に提出した日本の国別削減目標、NDC、この極めて低い削減目標ですら実現できないシナリオを政府は想定しているということだと思います。
資料二に、同じく資源エネルギー庁の二〇四〇年度におけるエネルギー需給見通し関連資料からシナリオ別エネルギー起源CO2排出量を添付いたしました。
ここにある、一、再エネ拡大、二、水素・新燃料活用、三、CCS活用などが十分進まない場合、右端のようにCO2排出量が増えるリスクシナリオになるということだと思います。
資料三に、産経新聞の記事が分かりやすかったので添付いたしました。
赤線引いていますけれども、リスクシナリオでは、二酸化炭素、CO2排出量は、既に公表済みのメインシナリオの一・五倍に達する、火力発電に頼るため、液化天然ガス、LNGはメインシナリオより最大四割多く必要になるということであります。
私は、これとんでもないシナリオだと思いますよ。こんな裏シナリオをつくることは、国内外の人々を欺くものであり、国際約束に対する誠実さを欠くものであると言わなければなりません。
産経新聞の記事には、リスクシナリオは再エネが拡大しないほか、燃焼時にCO2を出さない水素、アンモニアの燃料活用や、CO2を回収し地中に貯留するCCS技術が普及しないケースを想定するとあります。
要するに、三つのリスクがあるということなんですね。これは、経産省の説明よりも非常に分かりやすい説明がされております。
そこで、リスクとされるものを一つ一つ検証したいと思います。
まず、経産省に伺いますが、再エネが拡大しないリスクというのは一体どういうものですか。
○政府参考人(木原晋一君) 再生可能エネルギーに関しましては、今回のエネルギー基本計画においても拡大していくという見通しを出しております。さらに、技術革新を更に進めていくということで、ペロブスカイト型の太陽発電、あるいは、洋上風力におきましても、浮体式の洋上風力発電などの技術開発も全力で進めてまいりたいというふうに考えております。
○山下芳生君 ちょっと答えがこのリスクシナリオとかみ合っていないんですよ。
リスクがあるとしているんですよ。リスクがあって、予定したような技術開発ができなかった場合に、排出、温暖化ガスの排出量が増えちゃうと。その一つに再エネの技術が進展しない場合ってあるんですよ。今、進展します、頑張りますと言っているじゃないですか。どんなリスクがあるか聞いているんです。
○政府参考人(木原晋一君) リスクに関しましては、この外的な要因でございまして、国の政策としましては、このエネルギー基本計画、需給見通しに向けて、再生可能エネルギーの更なる拡充、それから技術開発を全力で取り組むという方向で進めてまいりたいと考えております。
○山下芳生君 あのね、事前にここは聞きますよとは言っていないんですけど、これリスクシナリオに入っていることだからね、リスクちゃんと言ってください。もう私の方で言いますよ。これまでさんざん経産省が再エネのリスクと言ったのは、日本は地理的条件が悪いと、太陽光を大規模に普及する適地がもうなくなってきたと、あるいは風力は、遠浅の海岸が少ないとかね、そんなことを言っていたんですよ。
だけど、太陽光発電は、屋根置き型、あるいは遊休農地の一部活用、ソーラーシェアリングだけでも大規模導入が可能だと、電力需要の一・五ないし二・三倍のポテンシャルがあると環境省が試算しております。さらに、風力発電は潜在的なポテンシャルが高く、浮体式などの洋上風力を計画的に進めればですよ、これは今、海上風力でも、もう離岸距離二キロ以内で、もう騒音とか低周波音で心配されることはありますけど、海外ではもう十キロ、二十キロ沖ですよ。浮体式であれば十分ポテンシャルがあるということになっているんです。
こういう再エネなら地域との共生は可能なんですね。まさに化石燃料輸入に、それから、日本は化石燃料輸入に頼っておるわけですから、再エネだったら経済効果は世界的に見ても大きいんですよ。遅れているからこそ、大きい。地域での再エネ導入は、地域のエネルギー収支の黒字化、町おこしにもつながると。
だから、私は、再エネというのはリスクではないと思うんです。日本にとって大きなポテンシャルであって、化石燃料と原発の支援ではなくて、再エネの大量導入こそ支援を尽くすべきだと思います。
次に、大きなポテンシャルを持つ再エネに対し、水素、アンモニアの燃料活用、あるいはCO2を回収し地中に貯留するCCS技術は間違いなく大きなリスクだと思います。これは当委員会で私が随分以前から指摘したことでもあるんですね。
例えば、水素、アンモニア、石炭の代わりに燃料にすればCO2が出ない、ゼロエミッション火力になるとさんざん言ってきましたけれども、しかし、一〇〇%水素、アンモニアで代替するというのはまずできない、まずは二〇%混焼からやろうと。しかし、アンモニアの混焼は今まだ実用化しておりません。先進国でアンモニア混焼を目指す国はありません。アンモニア一〇〇%の専焼が実現するまで石炭火力が残る、延命されるということになります。二〇%混焼でさえ、二〇三五年にどのぐらい普及するかも分からない。そして、アンモニアの調達ができるかどうかは疑問です。二〇%だけ混焼するのに必要なアンモニアの量は、毎年二千ないし二千五百万トンと試算されております。これは全世界のアンモニア市場規模に匹敵し、現実性に疑問が投げかけられています。
こういう、しかもその輸入するアンモニアはまず化石燃料由来から輸入するというわけで、全然このクリーンじゃないわけですよね。こういうリスクはいっぱいあるわけですよ。違いますか。
○政府参考人(木原晋一君) 水素、アンモニア発電及びCCSに関してのお尋ねでございます。
水素、アンモニアの混焼技術あるいは専焼技術は開発途上にございますが、政府としましても、GX基金なども使いながら、技術開発に最大限努めているところでございます。
今後、水素、アンモニアのサプライチェーンをしっかり構築していく、それから先進性のあるCCSプロジェクトの支援を行っていくということで脱炭素電源への新規投資を広く対象にしていきたいと考えておりまして、また、投資回収の予見性を確保するための長期脱炭素電源オークションという仕組みなども導入しておりまして、火力の脱炭素化についてもしっかり取り組んでまいります。
○山下芳生君 だから、リスクシナリオにリスクがあると書いておきながら、そのリスクをちゃんと言ってくださいよと、私の方から言っているのは否定できませんでした。
CCSだって、これは石炭、化石燃料の燃焼からCO2を分離、回収、貯留するわけですね。その際に物すごいエネルギーが必要です、水が。実際の回収率は六割から七割しかない。日本には油田がないので、本来、油田に二酸化炭素を圧入して、油田、油をいっぱい出すために使われている技術なようですが、しかしそういう可能性はもうない。漏れたときのリスクも非常に多いと。
ですから、リスクだらけなんです。だから、これは進まないんじゃないかということを認めてこのリスクシナリオをつくった。私は、これは本当に、ひどいというか、私が言っていたことを認めたなという面もあるんですね。いよいよリスクだということを認めた。化石燃料にしがみつきながら、石炭火力にしがみつくシナリオが、それを前提としたこういう新技術はなかなかできないということで崩れていっているということだと言わなければなりません。
最もリスクのないシナリオは、再エネを本当に本格的に普及することだということを申し上げて、終わります。