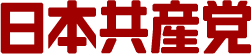○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
前回、所信質疑で政府のエネルギー基本計画に関するリスクシナリオの議論を経産省の方とさせていただきました。その際、アンモニア混焼のリスクについて聞きましたが、明確な答弁がなかったと記憶しております。
それで、今日も経産省の方に来ていただいておりますが、アンモニア混焼のリスク、経産省としてどう評価しておられるんでしょうか。
○政府参考人(木原晋一君) お答え申し上げます。
今回のエネルギー基本計画におけるいわゆるリスクシナリオというものがございまして、これに関するお尋ねでございます。
まず、この二〇四〇年のエネルギーミックスに関しては、二〇四〇年度温室効果ガス七三%、二〇五〇年カーボンニュートラル実現といった野心的な目標に向けて、将来からバックキャストする考えの下で、一定の技術進展が実現することを前提とした将来のエネルギー需給の姿を示しております。
これに対して、技術進展シナリオ、あるいはいわゆる御指摘のリスクシナリオでは、二〇四〇年度時点において再エネ、水素、CCSなどの脱炭素技術の開発が期待されたほど進展せず、コスト低減が十分に進まないような事態を想定したものでございます。
御指摘の水素やアンモニアに関して申し上げますと、製造技術などの脱炭素技術開発が期待されたほど進まないと、よってコスト低減が十分に進まないというような時点を、事態を想定しております。
より具体的に申し上げますと、メインのシナリオでは、水素等製造技術のコスト低減、効率向上が加速することを想定していまして、水電解、メタネーションに関する二〇四〇年度の設備コストとして、足下に比べて七から九割低減されることを想定しております。これに対して、いわゆるリスクシナリオでは、コスト低減が四から七割減にとどまるということを想定しております。
これに対して、現在、水電解装置による水素製造についてはグリーンイノベーション基金において大型化あるいはモジュール化などの支援しておりまして、水電解装置のコストを二〇三〇年度において二一年度から最大六分の一程度に削減することを目指しております。
こうした目標に鑑みれば、二〇四〇年度の想定コストを達成していくことができる可能性も十分にあるというふうに考えております。
引き続き、技術開発を進めながら、大規模なサプライチェーンの構築を通じて、供給と利用の拡大を両輪で図ることによってコスト削減の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○山下芳生君 頑張ればできる可能性もあるということとできない可能性もあるということでした。
ただ、もう前回も言いましたけど、気候変動、気候危機の現状というのは極めて深刻で、一・五五度を既にもう超えちゃったということですから、これ失敗許されないわけですね。失敗する可能性のある、私は高いと思います、そういう技術にいつまでもしがみついていて取り返しの付かないことにならないように、現在既に確立されている再エネ技術の大量導入で、日本の果たすべき役割、世界への貢献やるのがリスクゼロのシナリオにより近くなるということだと思います。
CCSについては、もう前回、私の方からコスト、リスクはかなり言いましたけど、その他に何かありますか、経産省さん。
○政府参考人(木原晋一君) CCSに関して申し上げますと、先ほどの御指摘しました、御指摘いただきましたこのリスクシナリオにおいては、CO2の回収、輸送、貯留等の技術開発が期待されたほど進展しないと。よって、コストが相対的に高い海外でのCO2貯留が進みにくい、こういう事態を想定したものでございます。
したがって、これに対しまして、経済産業省としては、分離回収の分野では排出ガス中のCO2濃度や圧力を踏まえた最適な技術の開発、輸送分野では海外への輸送を視野に入れた船舶の大規模化に向けた最適なタンク設計などの船舶輸送技術の確立、そして貯留分野では低コストなモニタリング技術の導入を目指した国内外での実証を進めております。
引き続き、CCS事業の自立化に向けたコスト低減に取り組んでまいります。
○山下芳生君 技術的な進展がなかなかできない場合ということと、既にその技術の進展があれば、海外でCCSを事業として推進して日本のCO2を貯留してもらうということも今の答弁には入っていたと思います。ただ、海外でCCSを事業展開して日本のCO2を貯留するということに対して非常に大きな懸念が表明されております。
資料の一を御覧いただきたいと思います。
これは、CCSは危険な目くらましで気候危機の解決策ではないという、世界の九十に及ぶ環境団体が齋藤経済産業大臣などに提出した意見書で、昨年の五月八日のものです。
冒頭の二行を見ていただいたら、私たちは、日本で排出された二酸化炭素を回収し、海外へ輸出、貯蔵するという二国間の炭素回収貯留、CCS事業が進んでいることに関して深い懸念を抱いていますと。三つ目、二〇二四年四月時点、インドネシア、マレーシア、オーストラリア等にCO2を輸出し貯留する事業の実現可能性を検討するために、日本の政府機関や企業によって署名された協定等が少なくとも十五件ありますと、四ページ以降に載っています、このような行いは気候危機を悪化させ、気候正義の原則に根本的に反していますと。
以下、幾つもの課題を並べた上で、三ページにちょっと飛んでいただきたいんですけれども、三ページの一番上、四番目の課題として、長期貯蔵の問題ですと。CCSが脱炭素化の実現可能な選択肢となるためには、炭素を安定した状態で永久に貯蔵できるようにすることが重要です、IPCCは、地質、陸地、海洋貯留層などにおけるCO2の貯蔵を説明するために永続的という言葉を使用しています、少なくとも二百年ないし三百年であると示唆する案もあります、そのような長期間の炭素隔離の維持を保証できる法制度は実際には実現可能ではありませんと、こうしているんですが、恐らく国内でも二百年、三百年先の貯留ですね、これを保証するということはなかなか難しいでしょうけれども、ましてや海外で二百年、三百年先まで責任を負うという制度はなかなかできないと思うんですね。
これはまた後で経産省の方に聞きますが、私、まず、まあまず経産省に聞きましょう、じゃ、これ。こういう懸念出ていますけど、技術的にこれクリアできます。
○政府参考人(木原晋一君) まず、海外におけるCCSにCO2を運んでいくという点でございますけれども、海外におきましては、過去の石油、天然ガス開発から得られた豊富な地質データによって、既に貯留ポテンシャルが明らかな地域がございます。その上で、貯留ポテンシャルに恵まれた国の中には、CCSに関する技術移転を求めたり、貯留場の操業の安定化や運営のための経験を獲得するためにCO2の海外からの受入れを積極的に提案、模索する国も複数現れております。こうした国に対して、そのニーズを踏まえてCCSに関する技術移転や貯留事業への参画、共同実施を含めて対応を検討し、我が国として、受入れ国の双方の経済成長やカーボンニュートラル実現に資するなど互恵的な関係となるように順次対話を進めてまいりたいと考えております。
その上で、CO2の漏えいのリスクに関して御質問がございました。国内に関しましては、この貯蔵、CO2が漏えいする可能性がある場合には貯留事業の許可を与えないですとか、あるいは、貯留を始めた時点からはその貯留事業者に対して貯留したCO2のモニタリングの義務、あるいは万が一漏えいが発生した場合の応急措置などを義務付けるなどをしております。
これは、海外のCCS事業に関してはどうかというところでございますけれども、日本からCO2を輸出し海外においてCCS事業を行う場合には、輸入国がロンドン議定書の締約国である場合には同議定書に基づいてモニタリングを含めた漏えい防止措置を講ずる必要がございます。また、輸入国がロンドン議定書の締約国でない場合においても、我が国から同議定書の要件と同じ措置を講ずるよう、二国間で措置をとってまいります。
いずれにしても、輸入国はロンドン議定書と同水準の厳格な措置を講ずることになるということでございます。引き続き万全を期してまいりたいと考えております。
○山下芳生君 そういう受入れの準備をしている政府があるということでしたけれども、例えば、マレーシアでは日本のCCSの受入れを推進する法案が議論されているというふうに承知しておりますが、市民社会は大反対しているんですよね。なぜなら、プラスチックの受入れをマレーシアはずっとやってきて、これ、NHKのスペシャルでもやっていましたけど、プラスチック、廃プラスチックを加工するような工場、中小・零細工場でしたけど、もう本当にさらされて、暴露されて、多くの方が健康被害にさいなまれているという姿が出ていました。だから、またプラスチックの二の舞になるんじゃないかと、二酸化炭素を受け入れたらですね、そういう市民からの非常に大きな声が出ております。
この資料の後ろの方に、どこの国の環境団体が、これ六ページ、七ページですけれども、最初に出てくるのはマレーシアなんですよ。十九のマレーシアの環境団体、市民団体が日本からのCCSの受入れを反対だと、危惧するのは、そういう歴史的な背景があるんですね。よく見る必要があると思います。
そこで環境大臣に伺いますが、三ページの下の方に、CO2を他の場所に投棄することは無責任であり、廃棄物植民地主義の一形態ですと、一番最後、日本は国際的な気候公約に沿って再生可能エネルギーに投資し、国内で大幅な排出削減に取り組むべきですと、こうあるんですが、この意見書は環境大臣にも宛てられた意見書なんですね。世界九十の環境団体から、大変重い意見書。廃棄物植民地主義の一形態と、これはしっかり受け止めて対応する必要があると思いますが、まず、この受け止め、いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の二酸化炭素の貯留適地には地理的な偏在性があることから、CCSの実施に当たっては、国内での二酸化炭素貯留を実現していくことに加えて、相手国政府の意思等を踏まえつつ、海外で貯留することも有力な選択肢の一つであると認識をしております。
○山下芳生君 私が今聞きたいのは、この、ここで言っていることなんですよ。まあいいでしょう。相手先の市民は非常に危惧しているということです。
それだけではありません。日本のCO2を東南アジアに輸出するCCS事業の推進に加えて、日本のために水素、アンモニア、LNGを作ってもらうということに加えて、東南アジアでもそれを使ってもらって火力発電の延命を推進しようとしている計画がたくさんあります。それがアジア・ゼロエミッション共同体構想、AZECの具体的な内容なんです。
この大きなA4の、ごめんなさい、A3、A3の資料には、二〇二二年十二月のAZEC、アジア・ゼロエミッション共同体の首脳会議の際に示された日本企業若しくは日本政府の機関が各国と覚書を結んだ案件、MOU案件の一覧です。これ見ていただいたら、アンモニア、水素、CCSなど石炭火力の延命の事業、あるいはLNGの拡大の事業など、化石燃料に対する支援が多くを占めています。ずっと見ていただいたら、その数、実に七十一案件が今検討されている案件なんですね。
これに対して、またA4の資料に戻っていただきますが、先ほどの続きの資料三なんですが、これは、二三年十一月、こういうやつですね、縦書きです、二三年十一月、あっ、十二月十五日、脱化石燃料を実現する輝ける機会を日本は逃してはならないと題する岸田総理大臣宛ての公開書簡、世界の市民団体、環境団体、八十九団体が共同で提出したものです。
これ、いっぱい書いていますけど、二ページ目の上の方を見ていただきたいんですが、日本は、東南アジアでは、水素、アンモニアの混焼やCCSなど、石炭、ガス、石油の使用を長期化させる技術を推進している、日本は東南アジアにおける化石燃料ガス、LNGの拡張に最大の資金提供を行っている国となっていると。それから、四段目なんですが、日本の化石燃料に基づく技術開発は、東南アジアの再生可能エネルギーへの移行を阻み、化石燃料の使用を長引かせるだろうと、こう述べています。
さらに、三ページ目の二段目見ていただいたら、化石燃料開発事業に対する日本の投融資は、既に東南アジア全域でコミュニティーと環境に大きな被害を与えている。フィリピンのヴェルデ島海峡、ここでは化石燃料ガス開発によって海洋生態系と水質が悪化し、その一部は日本が投融資したものであると。漁民は、魚の漁獲量が減るか、全く捕れなくなり、生活を維持するのに苦労している。さらに、化石燃料の燃焼によって引き起こされる大気汚染は、コミュニティーに多大な健康被害をもたらしていると。
浅尾大臣、これは環境大臣としてやはり見過ごすことができない、直視すべき事態だと思いますが、感想いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 化石燃料を日本としても二〇五〇年までにネットゼロにしていくという大きな流れの中で、そういったことを、日本国内のみならず世界的にそうしたことを推進していくということは、そのとおり、実現していくべき課題だというふうに考えております。
一方で、トランジションということが必要となってまいりますので、そのトランジションの間においては、より燃料効率のいいものを実用化していくと、そういった観点からアンモニア混焼といったようなものが存在するというふうに認識をしております。
○山下芳生君 さっきから聞いている一番大事なところにお答えがないんです。
既に日本の化石燃料関連技術の輸出、投融資でこういう健康被害、環境破壊が行われているということを、これ日本の環境団体だけじゃないです、世界の環境団体がですね、これ八十九団体ですけれども、先ほど読み上げたようなフィリピンなどでの実態を告発しているわけですね。環境大臣なんだから、日本の環境守っときゃいいというわけじゃないでしょう。やっぱり世界でも環境を守らなければならないと思うんですが、残念ながらこういうことが起こっているということについてコメントいただきたいんですよ。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今お答え申し上げましたけれども、二酸化炭素に限らず、そうした化石燃料を燃焼することによって、様々な、例えば硫化水素等が発生するといった場合には、その脱硫装置等をしっかりとそれは設置していかなければいけないということは、そういったことに取り組んでいくべきだろうというふうに考えております。
○山下芳生君 最後の行を見ていただいたら、日本はやるべきことをちゃんとやるべきだということなんですね。化石燃料ガス、水素、アンモニア、バイオマス、CCS、その他誤った対策への投融資を直ちに終了し、その代わりにコミュニティーのニーズを満たし、コミュニティーに被害を与えない再生可能エネルギーへの支援に転換すること。
これ、国内でも海外でも日本がやるべきは再生可能エネルギーへの支援なんだと、もうそっちの方向に行かないと、これはどう考えても無理があると、世界からも無理がありますよということが何度もこれ指摘されているわけでね。先ほど経産省の方からありました、リスクがあるんですよ、この技術の方が。やはりチェンジする必要があると。
そうじゃないと、資料の最後に載せていますけど、この大きな方で、JBICは、結局リスクシナリオの行き着く先は、先週も言いましたけど、世界からLNGを大量に買いあさってね、それを、今日本でも余っているのに更に買いあさって、輸出してもうけようというね、そういうことを、まあもうかりませんけど、コスト高いですからね。
ですから、そういう意味では、そういうもう展望のない道はやめて、先ほどの、この間の日米首脳会談でも、こういうやるべきことをやらないで、アメリカから、パリ協定から離脱するトランプ政権から、改めてLNGを買うということを約束しましたね。掘って掘って掘りまくるというアメリカから、買って買って買いまくるという日本では、余りにも、世界に背を向けることができないと、顔を向けることができないということを指摘して、大臣にもう少しかみ合った議論を期待して、次からは、質問を終わります。
ありがとうございました。