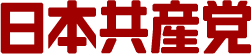○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
私からも、鳥獣保護管理法改正案について聞きます。
熊が市街地へ出没することが増え、熊による人身被害は、二〇二三年百九十八件、二百十九人と過去最多を記録し、六名の方が亡くなっています。現状では、市街地での銃猟は、同法三十八条に基づき禁止されています。例外的に、市街地での銃猟は、警察官職務執行法第四条に基づいて、人の命や身体に危害を及ぼし、緊急に対処が必要な場合に限り、警察官の命令によってのみ可能となっております。
資料一を御覧いただきたいんですが、これは秋田県内の住宅街に熊が出没したときの写真です。写真のように熊がぽつんといる場合、警察官職務執行法で対処できるんでしょうか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
警察官職務執行法第四条第一項におきましては、警察官は、人の生命又は身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされているところでございます。
委員お示しの写真のみでは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当する場面か否かを申し上げることは困難でございますが、例えば、周囲に人がおらず、人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがない場合などは警察官職務執行法第四条第一項の規定に該当せず、警察官がハンターに猟銃等を使用して熊等の駆除を命じることは困難であると考えるところでございます。
○山下芳生君 この写真だけでは判断できないが、周りにこの状況で人がいなければできないということですが、そういうことでどのような弊害が起きているんでしょうか。具体例を紹介していただけますか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。
現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。
このため、熊等の出没により現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されておりますが、例えば熊が建物に立てこもるなど、秋田県の事例でショッピングセンターに立てこもった事例が最近でもありました。そして、膠着状態にあるような場合では現行法では対処することができずに、地域住民が長期間にわたって不安な夜を過ごすなどの問題が生じております。
本法案では、このような背景を踏まえ、熊等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。
○山下芳生君 秋田市では、市町村職員から警察官に対して発砲の提案をしたけれども、緊急事態と判断されず、発砲命令が出されずに、その後、捕獲作業に当たった捕獲者が、繰り返しかみつかれたりひっかかれたりして指先を欠損するなどの重傷を負ったという例もあると承知しております。
現状では、警察官職務執行法を適用するかどうかは現場の警察官の判断になります。今回の法改正は、熊などによる人身被害を未然に防ぐ観点から、一定の条件を満たした場合に限り市町村長の判断で市街地の銃猟を可能とするものになります。それによって、ハンターが市街地でライフル銃を発砲する機会が増えます。ハンターからは、事故が起こった場合、責任を負わされるのではないかとの不安の声も出されています。
こうしたハンターの声にどう応えるんでしょうか、環境大臣。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 熊等が人の日常生活圏に出没した場合には、地域の関係者が連携して対応することが不可欠であります。その中でも、ハンターの皆様に安心して対応いただくことができる環境整備が重要であり、制度の検討に当たってハンターの方々の御意見もいただいてまいりました。
緊急銃猟は、市町村長が主としてハンターに委託して実施することとしておりますが、銃猟を行うことの決定や、そのための安全確保措置など、緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり、委託を受けたハンターが責任を負うものではありません。また、委託を受けたハンターには腕章等を着用していただき市町村長からの委託であることを明確にした上で、物損や万が一人身事故が生じた場合には、ハンターではなく銃猟を委託した市町村が補償や賠償を行うことについて制度的に担保することとしております。
こうした制度の内容については今後作成するガイドラインにおいても周知し、ハンターの皆様に安心して御協力いただけるようにしてまいりたいと考えております。
○山下芳生君 市町村に全ての責任を負わせていいのかと。国もしっかり責任を持つべきではないでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。
今回の改正案における緊急銃猟の制度は市町村長が責任を持って判断をするということになっておりますけれども、そもそも、やはりこの鳥獣政策自体がこれまでも地方自治体の責任において、あるいは対応において行われてきたところもありますのと、今回の緊急銃猟のような場合は緊急に対応をするということ、その地域の地形でありますとか熊の生息状況、その他の野生生物の生息状況も分かった上で対応をする必要がありますので、市町村長にそこの判断を委ねているところであります。
○山下芳生君 損害保険の保険料の交付金、保険料を交付金で支援するということがあるというのは聞いてはおりますけれども、今おっしゃったように、より広い意味で国の責任を果たしていく必要もあると思います。
私、猟友会の皆さんからいろいろ話伺ったんですが、趣味で狩猟を行っている方々の集まりというのが多いです。しかし、これ先ほどありました、北海道砂川市で、ヒグマを駆除した男性が住宅の方向に発砲したとして北海道公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されて訴訟になっているということもあります。
環境省の検討会での議論でも、今回の改正で一般の趣味の狩猟者に非常に重たい業務を担わせるのかという話にもなりかねないと懸念の声も上がっておりますので、改めて国として責任を負うことが大事だと思います。
次に、猟友会として出動するハンターの方々への日当の問題について聞きます。
法案では、市町村長は緊急銃猟を委託して実施させることができるとされております。家畜の牛を何頭も襲った熊、OSO18がいた北海道の猟友会、標茶町支部長からお話を聞きましたが、標茶町では半日出て六千円といいます。支部長は、お金の面で言えば、支部長という立場で若い人に出てくれとは言えない、それだけの保証はできないからなんですよと言われました。これは、働いている人がこっちに出たら、こっちの方が報酬が低いわけですよね。熊がスーパーに入り込んだ秋田市では半日で三千三百円と、今年度は四千円に引き上げるそうですが、自治体も引き上げたくても予算がないということがあるようです。
熊による被害の予防、警戒、駆除に当たる猟友会の皆さんからは、命懸けでやっているんだと、熊と対峙する精神的な負担感もあるんだと、ハンターの任務に対する報酬が余りにも低過ぎると言っておられました。
環境大臣、ハンターへの報酬は国がきちんと保証すべきではありませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 熊の出没対応に関するハンターの報酬については、熊の生息状況や出没状況等の地域の実情を考慮した上で地方公共団体において設定されております。
その上で、政府としては、環境省と農林水産省において、必要に応じ指定管理鳥獣対策事業交付金や特別交付税措置による財政支援を行っております。また、本法案の緊急銃猟についても、捕獲当事者の日当、経費等が市町村において適切に支払われるよう、環境省の交付金等で対応できるようにしてまいりたいと考えております。
引き続き、関係省庁が連携し、地域の実情に応じた必要な支援に取り組んでまいります。
○山下芳生君 ハンターの任務に、非常に重い任務に見合う報酬にするために国の責任を果たしていただきたいと思います。
私、この質問する上で、非常にこれやっぱり悩ましいんですね。これまでは、撃てという、そういう方向での質疑でした。しかし、やっぱり、本当にそれでいいのかということをやはり考える必要があると思うんですが、熊の市街地への出没がなぜ増えているのか、ここからやはり考えないと駄目だと思いますが、環境省、原因は何だと考えますか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。
熊が人里に出没する要因には、秋の主要な餌であるブナやナラなどのドングリが凶作により不足し、熊が餌を求めて人里まで行動範囲を広げたことが大きな要因の一つとして考えられております。
特に、令和五年度は、岩手、秋田、宮城、山形県で八月以降の熊の出没件数が増加いたしましたけれども、その要因の一つとして、東北地方においてブナやミズナラなどのドングリが凶作となり、餌不足になったことが考えられます。
○山下芳生君 二〇一三年にドングリの木の実が減少した、極めて減少したということが一つの原因だということは私も聞いております。ただ、それだけなのかということも考える必要があると思います。
熊は警戒心が強い動物だと言われております。クマ類保護及び管理に関する検討会が出した被害防止に向けた対策方針では、ヒグマやツキノワグマの出没要因で共通して指摘されているのは、林業従事者や狩猟者の減少によって森林内で活動する人口が減り、熊が森林内で人に追われる機会が減少することで人への警戒心が薄くなり、集落周辺まで分布が拡大していることが共通して指摘されております。
資料二は林業従事者数の推移を示したグラフであります。
一九八〇年の十四万六千人から二〇二〇年には四万四千人と、長期間減少し続けています。なぜ林業者がここまで減っているんでしょうか。
○大臣政務官(山本佐知子君) お答えいたします。
日本の林業従事者の長期的な減少傾向は、まず、木材価格の下落等により採算性が悪化した中、森林所有者の経営意欲の低下が生じました。そのために林業生産活動が停滞してきたこと、そして二つ目に、林業従事者の平均所得が全産業平均と比較して約百万円低く、また、労働災害発生率が全産業平均の約十倍であることなどが要因と考えられます。
このため、農林水産省としましては、所得向上と労働安全確保が必要と考えています。そのために、まず高性林業機械の導入、また路網の整備による林業経営体の生産性を上げ、そして収益力の向上を図るということ。次に、緑の雇用事業等による新規就業者の確保やスキルアップ。そして三番目として、林業労働安全衛生研修や労働安全衛生装備、装置の導入などへの支援を実施しています。これらの取組を通じまして、林業従事者の確保を図ってまいりたいと思います。
○山下芳生君 今お答えありました木材価格の下落ということが、ただ、じゃ、何でそんなになったのかといいますと、やはり木材の輸入自由化を進めた結果、安い外国産材が入ってきて国産材の供給が減少し、国内の林業が低迷を余儀なくされたというのが根本原因だと思います。そういう意味では、林業、国内林業の再生に向けて国産材の活用などの支援を強めることも熊出没対策にとって重要になるんだという観点で当たっていただきたいと思います。
本来、奥山に生息する熊が人里に下りてくるのはなぜか。資料三も見ていただきたいんですが、農村では、農業を仕事にしている基幹的農業従事者が二〇〇五年に二百二十四万一千人いましたけれども、二〇二〇年には百三十六万三千人ということで三九%減少しています。農家が減ることで耕作されない農地が増えると同時に、農地周辺の草刈りなどが行われなくなることで山と人里との見通しが悪くなると、ガサヤブが、というんだそうですが、ガサヤブが広がって熊から人の姿が見えにくくなって、熊の警戒心が薄れる要因の一つとなっていると。
大臣、農村から農家が減って、熊の生息地と人里との境界が曖昧になっていることも熊が人里に下りてくる一つの要因ではないかと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 熊が人里に出没する要因については、ドングリが凶作によって餌不足となることのほか、今御指摘がありましたように、農村がある中山間地域における人口減少や高齢化が進展し、耕作放棄や里山利用が減少するなど、人間活動の低下も要因の一つと考えられます。
熊対策は、人と熊とのすみ分けを図ることが重要であり、令和六年四月に環境省、関係省庁との取りまとめでまとめましたクマ被害対策施策パッケージに基づき、人の生活圏への出没防止のための追い払いや、放任果樹等の誘引物の管理への支援、針葉樹と広葉樹が混じり合った森林や広葉樹林への誘導といった熊の生息環境の保全整備など、捕獲に頼らない総合的な対策を進めてまいります。
○山下芳生君 私は、山村や農村の疲弊を招いた政治の責任は極めて重いと思います、本当に重いと思います、この面でも。猛省すべきだと思うんですが。農業は、食料を生産し、美しい景観を守るとともに、野生動物と人間との境界を保つという大事な役割を果たしていると思います。熊と人とのすみ分けが大事だというんだったら、農業、林業の再生に力を入れてこそだということも強調しておきたいと思います。
ちょっと時間が余裕ができたようなんで、私、三月三十日にNHKの「ダーウィンが来た!」が、この熊の問題、東京農工大の大学院、小池伸介教授らの研究グループ、チームの研究を追っかけて、捕獲した熊にGPSと首輪型カメラを付けてその行動を秋田で詳しく追いかけるという調査研究が放送されておりました。
やはり熊の生態をしっかり把握するということが大事だということなんですが、まだ途上だと思いますが、分かったこととして、今この人里に出てくる異常な行動の背景には山の中での深刻な食料不足があったと。先ほど言われたように、熊の主な食べ物であるドングリ類、ブナ、ミズナラ、コナラなどの実が、二〇二三年、東北各地でほとんど実らなかったと。ドングリの実が少なかったため、熊は十分な栄養が取れない。秋は冬眠前に体重を増やす大事な時期だが、それが難しい状況。山にいても飢えてしまうため、やむを得ず町へ移動するしかなかった。つまり、熊が町に出てくるのは、生きるために仕方なく行動しているという面が熊から見ればあると。こうした事実を知ることが、熊と人との距離感を保つ上で非常に重要だという指摘でした。
食べ物はなくなり、生きるために仕方なく町に来ているんだと、人間の出すごみ、生ごみ、果物の臭いなどが熊を引き寄せてしまっているということもあると、熊との距離を考えることは人間の暮らしそのものを考えることにもつながるんだという指摘でしたけど、やはりそうだと思います。熊が、人里に下りてきた熊にどう対処するかということももちろん大事ですが、下りてくる原因を究明して、いかに共生するかということも考えなければ、これはもうイタチごっこになるというふうに思います。
最後に、外来生物、クビアカツヤカミキリの防除対策交付金について聞きます。
クビアカは、梅、桃、桜などの樹木に寄生し、最悪の場合、木を枯らす外来生物であります。奈良県は吉野千本桜など桜の名所で有名ですが、さらに、川沿いの桜並木や公園、世界遺産である平城宮跡にある桜が観光資源の重要な柱となっています。
資料四、五にその被害の実態とクビアカの生態について書いてあります。
資料五は、奈良県天理市内のクビアカの桜被害の実態であります。
このクビアカがいる木の根元には、いるあかしとして、フラスと言われる幼虫のふんと木くずが混ざったものが出現します。ここに出現しているとおりなんですが。この付近では、桜が二十本ある中でもう十七本の桜の木がこういう被害に遭っているそうです。
クビアカが見付かった樹木の伐採や駆除などに環境省の特定外来生物防除等対策事業交付金が使われているんですが、いち早く対策に乗り出したい自治体からは、交付金が下りる七月まで待っていられないと、対策が遅れれば被害が拡大するとの声が上がっております。
環境省、交付金が下りるのを待たずに自治体が直ちに対策を取れるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。
御指摘の特定外来生物防除等対策事業におきましては、原則として交付決定に基づき事業に着手するものとしておりますが、地域の実情に応じ、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合は、交付決定前着手届を提出することにより交付決定を待たずに事業に着手することが可能となっております。
令和六年度では、全百三十二事業のうち六十七事業において交付決定前着手届が提出され、交付決定前に事業に着手されております。
引き続き、地域の実情に合わせて適切な支援を行ってまいりたいと考えております。
○山下芳生君 知られていないようなので、そういう声が出たので、是非周知いただきたいと思います。
終わります。