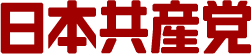企業・団体献金禁止こそ 政策活動費廃止法で討論

(写真)討論に立つ山下芳生議員=24日、参院本会議 |
自民党裏金事件をうけた改定政治資金規正法を含む「政治改革」に関する3法が、24日の参院本会議で可決、成立しました。日本共産党は、立憲民主党など6会派と共同提出した「政策活動費」廃止法には、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面禁止するものだとして賛成。自民党提出の改定政治資金規正法と、国民民主党と公明党が出した第三者機関設置法には反対しました。
日本共産党の山下芳生議員は討論で、自民党には政治改革の大前提である裏金問題の真相解明を進めるつもりが全くないと批判し、「政治改革の核心は企業・団体献金の禁止だ」と強調。企業が政治にカネを出すのは見返りを期待するからだと指摘し、「本来、国民のための福祉、医療、教育などに使われるべき税金が企業によってゆがんだ使われ方をしている」と述べ、「パーティー券を含め企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきだ」と主張しました。
山下氏は、自民党案は企業献金を温存した上で、外国人・外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、外資系企業のパー券購入の抜け道をつくっていると指摘。同法が国民の税金を政党に分配する政党助成金をペナルティーとして利用する制度創設を盛り込んでいる点も認められないと述べました。
国民・公明提出の第三者機関設置法案も、政治資金収支報告書に「適正」のお墨付きを与えるだけの隠れみのになる恐れがあるとして反対を表明。政治資金の収支は国民の監視のもとに置き、報告書は速やかに公開することこそ重要だと主張しました。
日本共産党が参院に提出した企業・団体献金全面禁止法案と政党助成法廃止法案は採決に付されませんでした。企業・団体献金禁止については引き続き議論を行うことになっています。