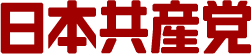○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
まず、気候変動の進行を抑えるための次期NDC、二〇三五年までに温室効果ガスの排出量を日本としてどこまで削減するかについて聞きます。
我が党は、二〇一三年比で七五%ないし八〇%削減する目標を掲げるよう求めて、十二月四日、代表質問で小池書記局長が石破総理に提案するとともに、環境省、経産省にも文書で要請をいたしました。一方、政府からは、二〇一三年比で六〇%削減という数字が提示されています。
浅尾環境大臣、気温上昇を一・五度に抑えるためには目標が低過ぎるのではありませんか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 気候変動は世界全体で取り組むべき喫緊の課題であります。我が国は、世界全体での一・五度目標の実現に向け、これまでも着実に排出量を削減してきております。
次期削減目標については、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合において御議論いただいているところであります。二〇五〇年ネットゼロ実現に向けた我が国の明確な経路を示し、排出削減と経済成長の同時実現に向けた予告可能性を高める観点から、直線的な経路を軸に検討を深めるべく、本日、第七回会合を開催し、次期NDCを含む地球温暖化対策計画の素案について御議論をいただく予定であります。
政府としては、脱炭素とエネルギーの安定供給、経済成長の同時実現を目指すとの考えの下、世界全体での一・五度目標の実現に向け、科学的知見やこれまでの削減実績等を踏まえつつ、年内に案を取りまとめ、我が国のネットゼロへの道筋をお示ししたいと考えております。
○山下芳生君 国連の気候変動に関する政府間パネル、IPCCの報告では、気温上昇を一・五度に抑えるためには、世界全体の排出量を二〇三五年までに二〇一九年比で六〇%削減する必要があるとしています。日本の目標は、二〇一九年比では五三%削減にすぎず、大きく乖離しています。
この乖離の最大の要因は、COの最大の排出源である石炭火力発電について、日本はG7で唯一期限を切った廃止計画を持たない国となっていることにあると思います。これでは気候危機回避に先進国として貢献できない、逆に足を引っ張ることになります。
資料一を御覧いただきたいんですが、これは、今、浅尾大臣が紹介された、日本のNDCを検討する審議会に提出された政府資料です。排出削減の経路が直線になっております。
資料二を御覧いただきたいんですが、これがIPCC第六次評価報告書、統合報告書に示された排出削減の幾つかの経路であります。この一番下の水色の曲線がIPCCのシナリオに基づく一・五度目標と整合する排出経路であります。スキーのジャンプ台のように、最初に急降下して、徐々に緩やかになります。下にへこんだ曲線となっています。
なぜこういう経路となるのか。世界の平均気温は、御存じのとおり、COの累積排出量に比例して上昇してきました。気温上昇を一・五度以下に抑えるためには、地球が許容できる残りの排出量、カーボンバジェットは極めて少ないと科学者が指摘しております。なので、この排出量が多く既存の技術で代替可能な発電部門などでの脱炭素化を急速に進めて、その後、運輸や製鉄など既存の技術では代替が難しい部門で新しい技術を開発しながら脱炭素化を進めるというものであります。
大臣はよくオントラックということをおっしゃいますが、オントラックと言うんだったら、この曲線に乗ることが大事ではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、次期NDCについては、世界全体での一・五度目標の実現に向け野心的な目標を掲げ、可能な限り削減を進めることとしております。それと同時に、政府としては、GXを通じ脱炭素とエネルギーの安定供給、経済成長を同時実現することが極めて重要と考えており、これらのバランスを踏まえた野心的な数字とする必要があります。
我が国としては、IPCC第六次評価報告書が提示する幅の中で削減目標を定め、世界全体の排出削減の取組に対してしっかりと役割を果たしてまいります。加えて、AZECの枠組みなども活用しながら、アジア地域を中心に世界の排出削減に取組を着実に進めてまいります。
○山下芳生君 幅の中でと言いますけど、一直線だと、この一・五度に整合する排出曲線には乗らないですよ。それから、世界全体と言いますけど、日本は先進国ですから、この水色の線よりもより野心的な削減目標を掲げる必要があると思うんですね。
それから、経済との整合性とおっしゃいましたけど、JCLP、日本気候リーダーズ・パートナーシップ、これは経済界の経営者の方も入っておられます。こういう団体が、世界に一・五度を諦めたのかと思われるこれは目標になっちゃうんじゃないかと。そうなりますと、これから日本製品を世界に輸出する際にも、そのエネルギー起源が石炭だと、これはもう取引から排除されかねないという、そういう経済界からの心配もあるんですね。そのことも紹介しておきます。
NDCを検討する政府の審議会には様々な立場
の方が委員として参加されています。しかし、そうした委員の意見が政府の政策決定にちゃんと反映されているのかとの疑問、批判が上がっています。資料三枚目、四枚目はそのことを紹介した記事であります。
審議会の委員で太陽光発電システムの販売、リース事業を行っている池田将太さんが、十月三十一日の合同会合に向けて、三十五年目標を一三年比七五%減とする提案を書いた意見書を提出したにもかかわらず、環境省から会合での読み上げを控えさせていただきたいと言われ、黙殺された形になりました。池田さんは、環境、経産両省には既に決まっているシナリオがあり、このとおりでいいですねと会合を進めたいだけなんだろう、この進め方で本当に正しい方向性の政策がつくられるのか疑問を感じていると訴えています。
浅尾大臣、こうした結論ありき、異論封じと指摘されている審議会の在り方、よしとされるんですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のNDCについては、本年六月から毎月開催しております中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合において、これまでも、各委員から目標や経路について幅広い御意見をいただいております。
このような議論の積み重ねの中で、いわゆる上に凸、下に凸の両論があったと認識しており、認識しておりまして、前回、十一月二十五日の合同会合において、事務局として直線的な経路を軸に検討を進めてはどうかと提案したものと聞いております。
いずれにしても、年内の地球温暖化対策計画の取りまとめに向け、本日から複数回審議会を開催し、委員各位の御意見を引き続き丁寧に聞きながら、更に議論を深めてまいりたいと考えております。
○山下芳生君 いや、無視された、黙殺されたという声が委員から出ているのに、それでいいんですかね。何かあります。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今御指摘された同委員が作成された意見書については、御本人との直接の相談の上、十月三十一日の会合での配付を取りやめ、延期し、その後、同委員から十一月二十五日の会合前までに再配付の依頼はなかったというふうに承知をしております。
○山下芳生君 怒っているんですよ、無視されたから。依頼がなかったじゃないですよ。
それからね、若い世代の皆さんが今そのことに非常に憤りを覚えて行動されています。
十二月に、結論ありきではなく科学や若者の声を聞いて、政府案二〇三五年までに温室効果ガス六〇%削減は不十分とするネット署名が急遽立ち上げられて、もっと意見聞いてほしいという署名運動が広がっています。趣旨は、これまで私たちは、今後深刻化する気候危機の最大の当事者である将来世代の意見を取り入れてほしい、温暖化対部策を話し合う審議会委員に若者を入れてほしいと求めてきました。しかし、ヒアリング先として若者団体が呼ばれることはあっても、実質的に議論に参加する機会はありませんでしたと、こういうことなんですね。このままでは、気候変動の影響を最も受けることになるであろう将来世代が自分たちの声をもっと聞いてと、議論に参加させてという叫びの声を上げている。
大臣、こういう若い世代の声にどう応えますか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 若い世代も含めて、気候変動の検討プロセスにおいては、様々なステークホルダーの声に耳を固めることが重要であります。
このため、審議会においては、専門分野、年齢層、性別等のバランスに留意しつつ、需要側を代表する委員にも参加いただいております。また、若い世代を含む様々な主体からのヒアリング結果も踏まえながら検討を進めております。
今後も、委員各位の御意見等を丁寧に伺うとともに、これまでいただいた御意見を踏まえつつ、政府としても、年内に案を取りまとめ、我が国のネットゼロへの道筋を示したいと考えています。
○山下芳生君 資料五は、経団連がエネルギー基本計画の改定に向けて出した提言に載っている図であります。先ほど、資料一で示した、環境省、経産省が示した排出経路、一直線の経路と全く同じ経路が経団連から提案されております。
浅尾大臣、経団連の声は丸のみするというのが環境省の立場ですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほども申し上げましたとおりでありますけれども、様々な意見がこれまでもなされてきておりまして、上に凸という意見もありますし、下に凸という合理的な意見もあったという中で、私どもとしては、G7の一員としてしっかりとその目標を達成していくという中で、こうした議論を積み重ねていく中で決めていくものだというふうに承知をしております。
○山下芳生君 まあその結論が経団連の提言とぴたっと一致しているということになっていることを私は提起しているんですよ、問題提起しているんですよ。
上に凸というのも、実は経団連も言っているん
ですね。上に凸というのは、石炭火力発電所はそのまんま維持しながら、そして技術革新、ゼロエミッション火力ができた頃に急に下がるという、これ非常に危ない、そんな技術ができるかどうか分からない。今既にある技術で、再エネ技術で、石炭火力はもうやめていくことが可能なのにずっと維持しながら、いつか急にネットゼロ二〇五〇年、危なくてしようがない。そのことを資料六で、同じ二〇五〇年ネットゼロでも排出経路によって全く累積排出量が変わってくるんだということを示しています。どちらが理にかなった曲線かというのは、これ見たらもう、はい、一目瞭然なんです。できることを今すぐ努力しないと、一・五度を維持できないですよということであります。
この経団連と同じ結果になったことを知ったフライデーズ・フォー・フューチャー・トーキョーの若い方は、出てきた数字は何も変わらなかったと、やはり経団連が勝つのかと驚き、悲しみ、絶望したと言いながらネット署名を立ち上げて今頑張っているんですね、若者の声を聞いてほしいと。
これ是非、若い世代の声、皆さんは、みんな科学の知見に基づいた危機感なんですよ。私が聞いたある高校生は、気候変動のことを考えると受験勉強も手に付かないとおっしゃっていました。ある若いお母さんは、世界がこのまま変わらないんだったら二人目の子供は産まないと、そうおっしゃった。そこまで若い世代は、五年後、十年後の気候危機のことを深刻に考えているんです。経団連の声を聞くのではなくて、科学の声、若者の声をちゃんと聞いて政策に反映させるべきだということを指摘しておきたいと思います。
次に、PFASについて聞きます。
各地でPFAS汚染への不安が広がっており、規制と対策の強化が求められていますが、食品安全委員会が六月に取りまとめた評価書でのPFOS、PFOAの許容一日摂取量の指標値は、欧米部の数十から数百倍の摂取を問題ないとする非常に緩い値となっています。
我が党の井上議員が、この点についてさきの本会議で聞きましたら、石破首相は、活用可能と判断される科学的根拠を基に耐容一日摂取量を設定したと答弁されていますが、活用可能と判断される科
学的根拠というのは、大臣、何でしょう。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のPFAS対策については、地域の方々の不安の声などを真摯に受け止め、昨年七月に専門家会議で取りまとめられたPFASに関する今後の対応の方向性に基づき、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めていくということとなっております。
御指摘のPFASに関する健康影響評価については、内閣府食品安全委員会が昨年二月にPFASワーキンググループを設立し、独立した立場で科学的に行われ、本年六月に耐容一日摂取量が設定されたものと承知しております。
耐容一日摂取量の設定に当たっては、諸外国が指標値の設定等のために用いた科学的知見も含めて、約三千報にも及ぶ文献情報を収集した上で、専門家が一つ一つ精査した上で健康評価、健康影響評価がなされたものと受け止めております。
○山下芳生君 その科学的に決めたということなんですが、いかにこの食品安全委員会の検討が、国際的に高く評価された、そしてPFAS規制基準のこの基になっている重要な研究成果を除外してきたかについて少し見てみたいと思うんですが、例えば国際がん研究機関、IARCが、PFOAについて最も高いランクのグループ1、人に対して発がん性があるというランクに分類した研究成果は、食品安全委員会の評価ではこれ排除されているんですね。
資料七は、この国際がん研究所の議論に参加した日本の専門家が、PFOAは発がん性のメカニズムに強い証拠が示された、誰一人反対しなかったと、国内の疫学的研究を早急に進める必要があると厳しい意見を載せている記事です。
資料八は、米国の環境保護庁、EPAが、PFOA、PFOSの飲料水の基準について、それぞれ四ナノグラムパーリットルの厳しい規制を設けたことを報じる記事であります。この規制値は、研究機関が世界の五千を超える研究の中から有効と判断した研究を基につくられたんですが、この研究成果も食品安全委員会の評価からは除外されています。さらに、国内の重要な研究成果も採用されておりません。
資料九、先ほど川田議員が紹介された日本の環境省が行っているエコチル調査に関わる研究で、子供の染色体異常への関連が指摘されたものであります。これを予防するためには、日本のPFOA、PFOSの飲料水の基準五十ナノグラムパーリットルをアメリカ並みの四ナノグラムパーリットルにすることが重要だという指摘もあるんですね。この研究は、環境省も承認して出された論文で、国際的にも非常に高く評価されています。この論文は食品安全委員会の評価書案の前に出された論文ですが、これは基準、対策に反映されませんでした。
こうして、重要な研究が不十分だ、あるいは限定的だとして日本の規制値を決める判断材料に含まれなかった。この食品安全委員会の評価が、水道水の水質基準にも反映されることになるわけですね。これは所管は環境大臣です。
資料十一を御覧、ちょっと一個飛ばして、十一なんですけれども、これは非常に重要な資料なんです。現在の食品安全委員会の評価書案で示されている一日耐容摂取量を摂取し続けた場合、推定される血中濃度がどうなるかということを京都大学の小泉先生が、もうPFASの第一人者ですけれども、推定して、研究してまとめたものです。それによりますと、米欧の専門機関が健康への影響が懸念されるとするレベルのはるか上になっちゃうと、三百九十三ナノグラムパーミリリットルにもなるんだということですね。これは、岡山の吉備中央町の住民で見られた余りにも高い血中濃度以上になるということなんです。
こういうことになるということを科学が警告している。健康に影響ないと、この値許容されたら、新たな安全神話の喪失になりかねないとみんな危惧しているんですが、環境大臣、水道事業を所管する大臣として国民の健を守らなければならない責任があるんですが、重要な研究成果を除外して緩い基準作っていいんでしょうか。どうですか。
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の点につきまては、環境省では、飲み水から健康リスクを減らすこと、摂取しないことを第一に、水道法に基づく水質基準への引上げを含め、来春をめどに、目途に方向性を取りまとめいくということは、先ほど申し上げたとおりであります。
また、汚染を広めないための対策技術に関する知見の収集を強化するとともに、汚染をつくらない、出さないため、国際条約を踏まえた製造規制や、PFOS等を含有する泡消火剤の管理なども徹底して進めてまいります。さらに、健康影響について国民の皆様に正しく知っていただくとも重要であります。
引き続き、様々な調査研究を通じて、PFASのリスクを明らかにしていくとともに、分かりやすい情報発信に努めていきたい。こうした総合的な対を通じて、人の命と環境をしっかりと守ってまいります。
○山下芳生君 知見があるのに採用されていないんですね。答えがありませんでした。
日本では、気候危機でもPFSでも最新の科学的成果が取り入れられず、科学的装いを取りながら、国際的に見ても低い目標、緩い基準が採用されています。地球の未来を守る、国民の命を守る立場で謙虚に科学と向き合うのか、特定企業の利益を守るために科学を利用するのか、政治にそのことが問われていることを指摘して、質問を終わります。