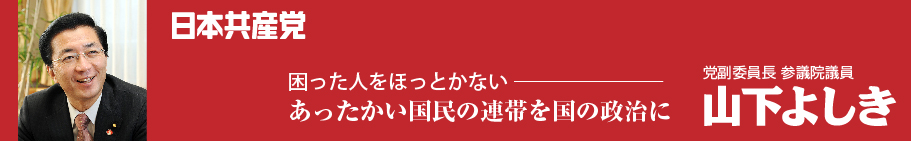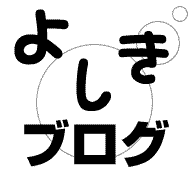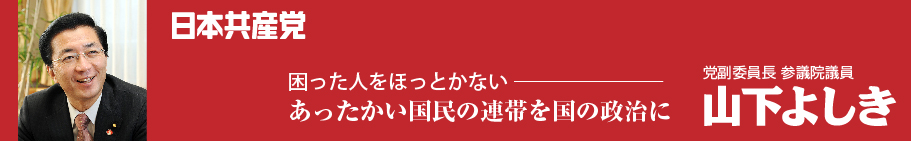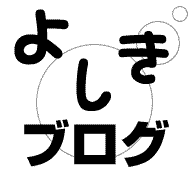2012年01月19日
18日、桜島と霧島山(新燃岳)の火山噴火災害の視察を行いました(参院災害対策特別委員会)。鹿児島県を訪ねたことは何回かあるのですが桜島に渡ったのは今回が初めて。もうもうと上がる噴煙を間近に見ると活動中の火山の迫力を感じます。
 桜島は昨年の爆発的噴火回数が996回と過去最高を記録。今年もすでに119回とそれを上回るペースで、近く大爆発が起こるのではないかと心配されています。鹿児島市、鹿屋市、垂水市、霧島市の首長や議長から現状と要望を聞かせていただきました。
桜島は昨年の爆発的噴火回数が996回と過去最高を記録。今年もすでに119回とそれを上回るペースで、近く大爆発が起こるのではないかと心配されています。鹿児島市、鹿屋市、垂水市、霧島市の首長や議長から現状と要望を聞かせていただきました。
桜島の場合、火山灰による被害が大きい。農業や漁業の生産物に降った灰がくっついて商品価値が下がったり、子どもたちが窓を閉め切った教室の中で遊ばなければならないなど、現地でなければわからない苦労があります。
 火山灰は雨などの水分を含むととても重たくなるとのこと。私も実際に持たせてもらいました。レジ袋に入ったこの量でなんと14kgの重さ。両手でないと持ち上げるのも難しい。個人宅地内の降灰除去に補助がないため、高齢世帯では作業ができす積もった灰が放置され床の高さまで来ることもあるといいます。せめて高齢世帯だけでも公費で除去できないものかと感じました。
火山灰は雨などの水分を含むととても重たくなるとのこと。私も実際に持たせてもらいました。レジ袋に入ったこの量でなんと14kgの重さ。両手でないと持ち上げるのも難しい。個人宅地内の降灰除去に補助がないため、高齢世帯では作業ができす積もった灰が放置され床の高さまで来ることもあるといいます。せめて高齢世帯だけでも公費で除去できないものかと感じました。
 ★桜島にある京都大学防災研究所付属火山活動研究センターも視察。地盤変動を中心に多角的な観測をしています。噴火を予知できる確立は7割とのことでした。すごい。
★桜島にある京都大学防災研究所付属火山活動研究センターも視察。地盤変動を中心に多角的な観測をしています。噴火を予知できる確立は7割とのことでした。すごい。
★霧島山(新燃岳)は昨年1月26日、約300年ぶりに本格的なマグマ噴火が発生し、気象庁は噴火警戒レベル3(入山規制)を発表しました。爆発的噴火が13回。大きな噴石が3.2kmまで飛散しました。「空振」という現象も起こり被害がありました。
現在、小康状態ですが、マグマだまりが再び膨張に転じており、火山活動は再び活発化する恐れがあります。霧島山の周辺5市2町(宮崎県都城市、小林市、えびの市、高原町、鹿児島県霧島市、曽於市、湧水町)でつくる環霧島会議の各首長、河野俊嗣宮崎県知事からお話をうかがいました。大量の火山灰が噴出したためロードスイーパーでは間に合わずパワーショベルで降灰除去した、一番の心配は火山灰による土石流の発生だったとのことでした。
 感心したのは、環霧島会議が年2回行われており、そこで2009年につくった「霧島火山防災マップ」が昨年の噴火の際とても役に立ったという話です。(写真は環霧島会議会長でもある前田終止霧島市長と)
感心したのは、環霧島会議が年2回行われており、そこで2009年につくった「霧島火山防災マップ」が昨年の噴火の際とても役に立ったという話です。(写真は環霧島会議会長でもある前田終止霧島市長と)
活火山といっても300年も本格的噴火のなかった霧島山。住民には「美しい山」という意識が定着していました。環霧島会議では、「それでも万万が一ふるさとの山が噴火したらどうなるか、専門家の協力も得て防災マップをつくろう」と議論し作成したそうです。
防災マップには、「今後噴火口となる可能性の高い4箇所」「規模の大きな噴火が起こった場合の災害区域予測図(4パターン)」「噴火で起きる現象(噴石、火砕流・熱風、溶岩流、降灰、火山泥流)」「いざというときの心得」などがわかりやすく示されています。噴火で起きる現象には、三宅島や伊豆大島など他の火山が噴火した際の写真が挿入されていました。
この防災マップができて2年後、写真と同じ現象が目の前で実際に起こったのです。日高光浩高原町長は、「このハザードマップにもとづいて熱風の避難勧告を出すことができた」と語られましたが、全国に広げるべき大変教訓的な話だと思います。
長峯誠都城市長が、「この土地でこの自然とともに生きていく覚悟です」とおっしゃったように、この国は、地震・火山活動と将来にわたって共存しなければならない宿命をもつ国です。桜島や霧島山周辺の人々の奮闘と課題は、この国全体で支え取り組まなければならないものです。
観測体制の強化、防災施設の充実、住民参加の避難体制づくり、被災者の生活を支える公的支援の拡充など、国政での役割を果たしたいと思います。