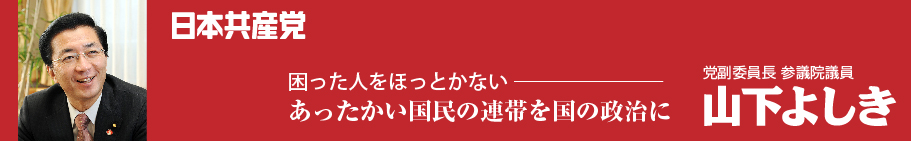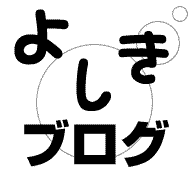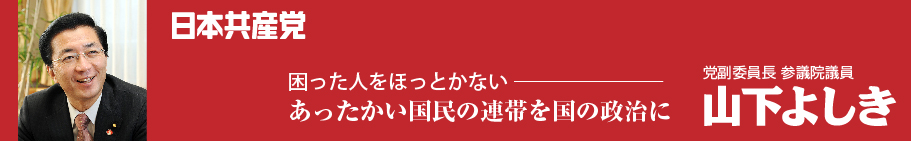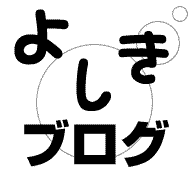あぁ、文化予算の貧困 東京国立博物館・東京文化財研究所を視察
2010年05月10日
昨年開催された「国宝 阿修羅展」で興福寺の阿修羅像に見入ってしまったのは東京国立博物館でした。そのときの入館者数は94万人。ちなみに歴代1位は1974年の「モナ・リザ展」の150万人、2位は1965年の「ツタンカーメン展」で129万人、「阿修羅展」は3位だそうです。
行政監視委員会の視察で、上野公園にある独立行政法人国立文化財機構を訪ねました。同機構は、2007年4月に国立博物館と文化財研究所が統合して成立しました。東京、京都、奈良、九州の4つの国立博物館と、東京、奈良の2つの文化財研究所の6施設から成り立っています。
きょうはいつも見ることはできない博物館の舞台裏を見せていただきました。
日本・東洋の美術品の多くは大変脆弱で、温度、湿度、光など環境の変化に強く影響されるため、東博では文化財をいたわりながら公開するという課題に取り組んでいます。そのために、最新の知識・技術を駆使して展示室や収蔵庫を整備するとともに、劣化した文化財の適切かつ計画的な修理(毎年100件前後の本格修理、1000件を超える対症修理を実施)を進めています。
 修理を行う部屋では、屏風の本格修理の準備が行われていました。専門的な知識・技能、そして経験を要する仕事ですが、修理にあたる人は3〜5年契約とのことでした。いいのかなあ。
修理を行う部屋では、屏風の本格修理の準備が行われていました。専門的な知識・技能、そして経験を要する仕事ですが、修理にあたる人は3〜5年契約とのことでした。いいのかなあ。
書物の収蔵庫にも入らせていただきました。奈良時代からの膨大な数の書物がヒノキとガラスの書庫に保管されています。ところが、予算の関係で空調は24時間運転できず8時間の部分運転だそうです。ルーブル美術館や大英博物館では考えられないことです。
 文化財研究所も視察しました。ここは、シックハウスならぬシックミュージアムの調査研究を行っている部屋。温湿度、光などと文化財の劣化の関係を調べ、環境を評価して劣化を防止するための研究をしています。全国各地の博物館から「空気のサンプル」が送られてきて分析、助言もしているそうです。
文化財研究所も視察しました。ここは、シックハウスならぬシックミュージアムの調査研究を行っている部屋。温湿度、光などと文化財の劣化の関係を調べ、環境を評価して劣化を防止するための研究をしています。全国各地の博物館から「空気のサンプル」が送られてきて分析、助言もしているそうです。
 こちらは、高松塚古墳、キトラ古墳などの壁画の劣化にかかわる調査を行っている部屋。壁画に発生したカビを取り除くための方法を研究するために、同じカビを何年もかけて培養し、壁画と同じ材質の漆喰に繁殖させてから、除去方法を見出す予定とのこと。2つとない文化財の保存には予算と時間がかかると実感しました。
こちらは、高松塚古墳、キトラ古墳などの壁画の劣化にかかわる調査を行っている部屋。壁画に発生したカビを取り除くための方法を研究するために、同じカビを何年もかけて培養し、壁画と同じ材質の漆喰に繁殖させてから、除去方法を見出す予定とのこと。2つとない文化財の保存には予算と時間がかかると実感しました。
機構の役員のみなさんとの質疑で、2001年に独立行政法人化されて変わった点を聞くと、「よくなったことは、入館者を“お客様”と呼ぶようになったことと、予算費目の縛りがなくなったこと。しかし、予算総額は削られた」とのことでした。
実際、東京国立博物館の年間予算額は22億円(09年度、8割が税金、2割が入館料などの自己収入)。大英博物館は107億円(08年度)、ルーブル美術館は288億円(08年度)。まさにケタ違いの少なさです。年間入館者数の違い(東博は200万人、ルーブルは800万人)を差し引いて考えても日本の文化予算の実態はお寒い限りです。
しかも、新政権の「事業仕分け」の対象に博物館も入っていて、先日も「仕分け人」から、「美術品収集の拡充はOKだが国費は出さない。自ら稼ぎなさい。博物館のフロアを貸しているレストランやミュージアムショップに競争原理を取り入れなさい」と指摘されたといいます。
う〜ん。これから何千年も先の後世の人々に、日本の歴史、伝統文化を保存し継承していく事業を、当面の財政事情だけで「仕分け」していいのでしょうか?
日本の文化予算を削る前に、米軍への思いやり予算を削ってよと、国宝や重要文化財を含む10数万点の収蔵品が叫んでいるように思えました。