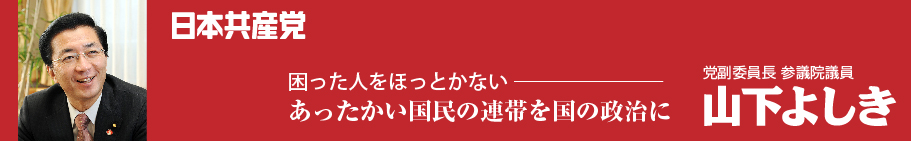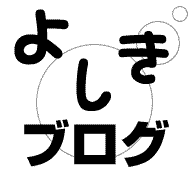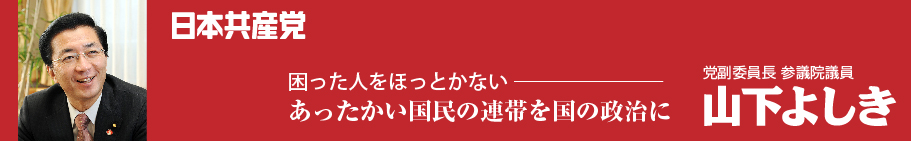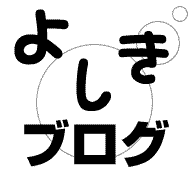これはなくしちゃいけない! 雇用・能力開発機構「ポリテクセンター」を視察
2010年05月07日
 これはなくしちゃいけません。独立行政法人雇用・能力開発機構神奈川センター(ポリテクセンター関東)を視察しての実感です。
これはなくしちゃいけません。独立行政法人雇用・能力開発機構神奈川センター(ポリテクセンター関東)を視察しての実感です。
「すべての働く方々がその能力を発揮し、雇用と生活の安定が図れる社会の実現をめざして」(同センター業務案内パンフ)とのスローガンのもと、求職者が早期に就職できるよう様々な職業訓練を行なっています。しかも、受講料は無料。経費は雇用保険事業から拠出されます。
 花田英一・統括所長にセンター内を案内してもらいました。まずは「建築CADリフォームコース」。自分たちで引いた図面をもとに、住宅の施工実習をしていました。受講生は若い女性が多かった。
花田英一・統括所長にセンター内を案内してもらいました。まずは「建築CADリフォームコース」。自分たちで引いた図面をもとに、住宅の施工実習をしていました。受講生は若い女性が多かった。
 図面の前で実習過程を説明してくれた指導員も女性の方でした。建築業界は、分業制でありながら、互いの連携や理解が重要となるので、チームで施工実習しているとのことでした。
図面の前で実習過程を説明してくれた指導員も女性の方でした。建築業界は、分業制でありながら、互いの連携や理解が重要となるので、チームで施工実習しているとのことでした。
 廊下に貼ってあった求人票。ハローワークからの情報とともに、企業からセンターに直接来る求人も少なくありません。地域の企業に有能な人材を送り出してきたことへの信頼の証です。
廊下に貼ってあった求人票。ハローワークからの情報とともに、企業からセンターに直接来る求人も少なくありません。地域の企業に有能な人材を送り出してきたことへの信頼の証です。
 続いて「機械CAD/CAMコース」。ものづくりに必須要素である2次元、3次元CADによる機械製図、NCプログラム、マシニングセンタによる加工を学びます。
続いて「機械CAD/CAMコース」。ものづくりに必須要素である2次元、3次元CADによる機械製図、NCプログラム、マシニングセンタによる加工を学びます。
 受講生たちが作ったプラスチック成型用の金型。実際にプラスチック製品を射出成型するところまで実習します。実習室には高額の大型機械がたくさん並んでいて、これは民間ではできない職業訓練だなと感じました。
受講生たちが作ったプラスチック成型用の金型。実際にプラスチック製品を射出成型するところまで実習します。実習室には高額の大型機械がたくさん並んでいて、これは民間ではできない職業訓練だなと感じました。
 6カ月の受講修了時に、自分たちが学び実習したことはなにか、どんなモノを作ったか、一冊の報告書にまとめます。これを持参して企業の採用面接に臨むと、自分のもつ能力についての大きな説得力になるとのことでした。ちなみに09年度の「機械CAD/CAMコース」修了者の就職率は96・7%だそうです。すごい。
6カ月の受講修了時に、自分たちが学び実習したことはなにか、どんなモノを作ったか、一冊の報告書にまとめます。これを持参して企業の採用面接に臨むと、自分のもつ能力についての大きな説得力になるとのことでした。ちなみに09年度の「機械CAD/CAMコース」修了者の就職率は96・7%だそうです。すごい。
 授業時間は終わっているのに金属加工用汎用機械のまわりに集まって指導員の説明を聞く受講生たち。みなさん若い。そしてとても真剣です。
授業時間は終わっているのに金属加工用汎用機械のまわりに集まって指導員の説明を聞く受講生たち。みなさん若い。そしてとても真剣です。
 「ビル設備コース」の実習室は配管がずらり。空調、熱源、給排水、電気、防災、衛生設備など、ビル設備を維持・管理する技術者には広い専門性が必要です。
「ビル設備コース」の実習室は配管がずらり。空調、熱源、給排水、電気、防災、衛生設備など、ビル設備を維持・管理する技術者には広い専門性が必要です。
 トイレ室の床下の排水パイプの管理技術も身につけます。「ビル設備コース」は中高年の受講生が多いとのことでした。
トイレ室の床下の排水パイプの管理技術も身につけます。「ビル設備コース」は中高年の受講生が多いとのことでした。
 「電気設備コース」では、設計から加工、配線、検査、点検までの一連の作業を通じて実践力を習得します。仮想エレベーターの製作実習(写真)も行ないます。
「電気設備コース」では、設計から加工、配線、検査、点検までの一連の作業を通じて実践力を習得します。仮想エレベーターの製作実習(写真)も行ないます。
 ここでも授業が終わったあと受講生たちが自習していました。指導員もつきあいます。ほんとに熱心です。
ここでも授業が終わったあと受講生たちが自習していました。指導員もつきあいます。ほんとに熱心です。
ポリテクセンター内を一回りしていちばん感じたことは、各コース(10人〜32人)の受講生のみなさんの習得意欲の高さです。わずか6カ月または10カ月の訓練期間でそれぞれの職業分野で必要な知識・技能・資格をほとんどゼロから身につけるのですから驚きです。
09年度の全コース合わせた就職率(訓練終了後3カ月以内に就職した人の実績)は81・8%。リーマンショック前は90%だったそうです。ポリテクセンターでの職業訓練が求職者の早期就職にいかに役立っているかを物語っています。
しかも、紹介したように受講料は無料。受講中は雇用保険給付が延長されるので生活費にも困りません。ですからポリテクセンターで訓練を受けることを希望する求職者は多く、ハローワークを通じての受講申し込みは平均4・2倍の倍率だそうです。就職するより入所するほうが難しい状態です。
派遣や期間工など人間をモノのように使い捨てる大企業の身勝手をやめさせること、そのために労働者派遣法の抜け道のない抜本改正を行なうこととあわせて、こうした機能を持つ公共職業訓練施設をいっそう拡充し、離職者の職業能力を高めて早期就職を支援することは、私たちの社会にとって最優先課題のひとつだと痛感しました。
ところが、政府は、「雇用・能力開発機構の廃止について」という旧政権時代の閣議決定(08年12月24日)にもとづいて、全国に61カ所あるポリテクセンターを都道府県等に移管しようとしています。しかし、地方財政の深刻さを考えるなら事業の継続が困難になることは容易に想像できます。そんなことになれば「雇用と生活の安定が図れる社会の実現」に完全に逆行します。
視察中、声をかけてくれた若い受講生の一人も、「就職したいです」とハードな訓練メニューにくらいつく気持ちを語りながら、ポリテクセンターがなくなるかもしれないことを心配していました。
来週予定される独立行政法人通則法改定案の審議で政府の姿勢をただしたいと思います。