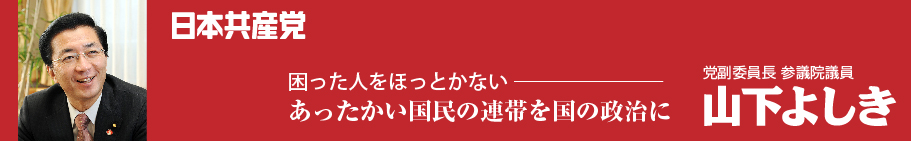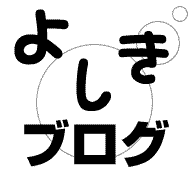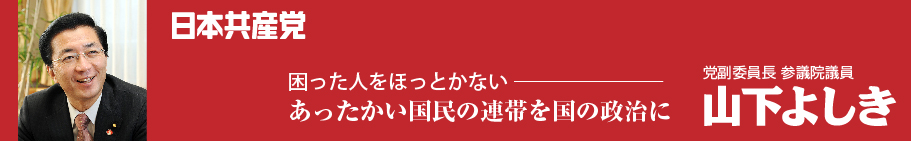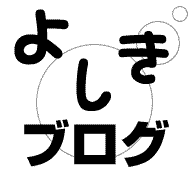ニュージーランド・オークランド市で「教育改革」調査
2009年12月14日
 ニュージーランドに到着しました。きょう、成田からの直行便で降り立ったのはニュージーランド北島の北部にある都市・オークランド市。南半球の季節は初夏。とてもさわやかに感じます。
ニュージーランドに到着しました。きょう、成田からの直行便で降り立ったのはニュージーランド北島の北部にある都市・オークランド市。南半球の季節は初夏。とてもさわやかに感じます。
ニュージーランドの面積は日本の4分の3。人口は432万人で大阪府民の半分です。長年、酪農品を輸出することを基本にした経済政策をとってきました。人々はおおらかでやさしく、特別に金持ちにならなくてもいい、家の近くで働いて暮らせればいいという気風が支配的だったといいます。
ところが、20年ほど前に、「規制緩和・市場原理主義・民営化」路線を日本に先駆けて採り入れて以降、ニュージーランドの人々の雰囲気が大きく変わった、競争的で、顔つきまで変わった、と20年前のニュージーランドと今日のニュージーランドをよく知る人から聞きました。
そのニュージーランドでも、行き過ぎた規制緩和路線の是正、たとえば、いったん郵政を民営化したものの、国民の金融機関がなくなってしまい、買い戻して国営のキウイバンクを設立するなどの動きも起こっています。
少し遅れて同じ道に進んだ日本でも、行き過ぎた規制緩和・民営化路線が総選挙で国民の審判を受け、郵政民営化の見直しが始まったことは、偶然ではなく、世界の流れなのでしょう。
 ★というわけで、大変興味深い国なのですが、今回の調査目的は「教育改革」です。まずは、教育省オークランド事務所を訪ね、アディン所長にお話を伺いました。
★というわけで、大変興味深い国なのですが、今回の調査目的は「教育改革」です。まずは、教育省オークランド事務所を訪ね、アディン所長にお話を伺いました。
ニュージーランドでは、1989年に大掛かりな「教育改革」が行われました。その柱は2つあるようです。ひとつは、教育委員会制度を廃止して、各小・中・高校ごとに「学校運営理事会」(Board of Trustees, BOT) を設けたこと。各BOTは、保護者代表5人、校長、教職員代表1人、生徒代表(高校のみ)1人から構成されます。BOTの役割は、教育カリキュラムの作成、教職員の採用、学校予算の立案・運用などで、とても大きな権限があります。
もうひとつは、それまで高校の卒業資格試験の合格率を50%程度にしていたことを改め(以前は失敗しても高収入の就職先があったが、それがなくなってきた)、あらたな「教育達成度国家資格」(National Certificate of Educational Achievement, NCEA)を導入したこと。これで生徒の80%は成功したがもっと高くする必要がある、とくにマオリ、ポリネシア系の学生で失敗している人が多く、底上げをはかる必要があるとのことでした。
アディン所長自身「教育改革」当時、校長先生だったそうで、「地震のような大きな変化だった」といいます。こうしたNZの「教育改革」の成果や問題点については、これからの調査で見えてくればと思います。
★次に訪問したのは、マクレインズ・カレッジ(上の写真。日本の中学2年生から高校3年生までが学んでいます。佐藤泰介団長と)。ベントレイ校長が案内してくれました。小高い丘の上にある学校からは真っ青な海が眺望でき、広々とした芝生のグラウンドも美しく、とにかくすばらしいロケーションです。
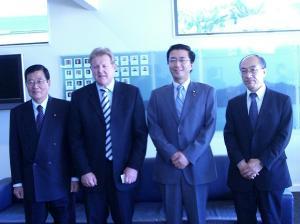 ニュージーランドでは97%の学校が公立だそうですが、高校までは授業料は無償(!)です。入学試験もなく(!!)、地域に住む子どもなら優先的に入学できます。これは日本と比べて文句なしにいい。保護者は、年間2万円~3万円の寄付金を払っているとのことでしたが、それでも日本の公立高校の授業料約12万円に比べればはるかに安い。ただし、積極的に受け入れている留学生の授業料は年間100万円ほどで、学校財政の重要な部分となっています。
ニュージーランドでは97%の学校が公立だそうですが、高校までは授業料は無償(!)です。入学試験もなく(!!)、地域に住む子どもなら優先的に入学できます。これは日本と比べて文句なしにいい。保護者は、年間2万円~3万円の寄付金を払っているとのことでしたが、それでも日本の公立高校の授業料約12万円に比べればはるかに安い。ただし、積極的に受け入れている留学生の授業料は年間100万円ほどで、学校財政の重要な部分となっています。
 全校生徒2500人(うち303人留学生)のマクレインズ・カレッジの教育で大きな特徴となっているのが「ファナウ・ハウス」(「ファナウ」とはマウイ語で「家」の意味)と呼ばれる制度。全校生徒を8つの「ハウス」に分け、入学してから卒業するまで(13歳から18歳まで)の5年間を同じ「ハウス」(建物)で学びます。5年間同じ「ハウス」で学ぶとシニアとジュニアの交流ができ、社会性やリーダーとしての役割も身につくのだそうです。
全校生徒2500人(うち303人留学生)のマクレインズ・カレッジの教育で大きな特徴となっているのが「ファナウ・ハウス」(「ファナウ」とはマウイ語で「家」の意味)と呼ばれる制度。全校生徒を8つの「ハウス」に分け、入学してから卒業するまで(13歳から18歳まで)の5年間を同じ「ハウス」(建物)で学びます。5年間同じ「ハウス」で学ぶとシニアとジュニアの交流ができ、社会性やリーダーとしての役割も身につくのだそうです。
こうした特色ある教育内容を決めるのも「学校運営理事会」。ベントレイ校長は、「保護者代表の位置が非常に大事」「保護者の中の法律家、公認会計士、建築家など専門家からボランティアでアドバイスがもらえる」と語ります。
校長先生は、「なにより生徒のパフォーマンスが大事。生徒が試験に成功することだ」とも強調します。実際、海外のトップレベルの大学に合格するために、NCEAとは別のケンブリッジ国際試験を70%の生徒が受験するそうで、生徒の大学進学率はなんと97%(全国平均は40%)。超進学校です。
入学試験もない、地域の子ども優先の公立高校で、どうしてこんなことが可能なのか?教育内容と環境のなせる業なのか、それともこの学校のある地域の特殊性なのか?そこはまだよくわかりません。
 ★次に訪問したのは、オークランド日本語補修学校。オークランドに住んでいる日本人の子どもたち(小中学生)を中心に、日本の学校と同じ教科書を使って国語、算数、理科、社会を教えています。昼間は、地元の学校でニュージーランドの子どもたちと一緒に授業を受け、放課後、この学校にやってきます。ちょうど小学生の男の子が「年賀状」づくりをしていました。教室の壁には、子どもたちの将来の夢がいっぱい書いてありました。
★次に訪問したのは、オークランド日本語補修学校。オークランドに住んでいる日本人の子どもたち(小中学生)を中心に、日本の学校と同じ教科書を使って国語、算数、理科、社会を教えています。昼間は、地元の学校でニュージーランドの子どもたちと一緒に授業を受け、放課後、この学校にやってきます。ちょうど小学生の男の子が「年賀状」づくりをしていました。教室の壁には、子どもたちの将来の夢がいっぱい書いてありました。
 海外で暮らす日本の子どもたち、日本とゆかりのある子どもたちに、日本語や日本の文化を教えることは、グローバル化・多様化する国際社会のなかで大変意義のあることだと思います。日本政府から教師の人件費は補助されていますが、ボランティアによる学校運営は苦しい。保護者が手作業で敷地の整備をしていました。もっと財政的な支援が必要だと感じました。
海外で暮らす日本の子どもたち、日本とゆかりのある子どもたちに、日本語や日本の文化を教えることは、グローバル化・多様化する国際社会のなかで大変意義のあることだと思います。日本政府から教師の人件費は補助されていますが、ボランティアによる学校運営は苦しい。保護者が手作業で敷地の整備をしていました。もっと財政的な支援が必要だと感じました。