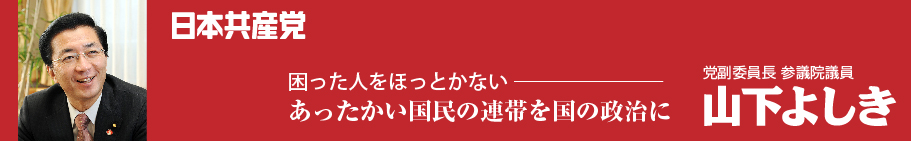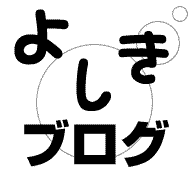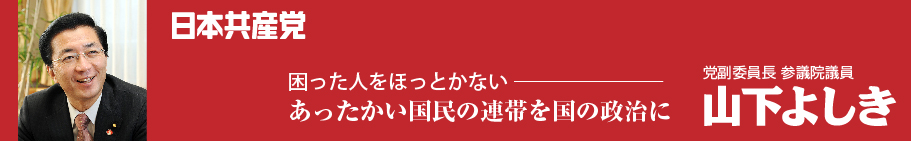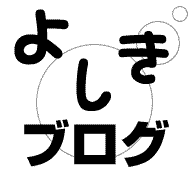2009年05月25日
 白熱した論戦になりました。予算委員会で「生活保護の母子加算を復活せよ」「児童扶養手当を父子家庭にも支給せよ」と迫りました。
白熱した論戦になりました。予算委員会で「生活保護の母子加算を復活せよ」「児童扶養手当を父子家庭にも支給せよ」と迫りました。
この4月から廃止された生活保護の母子加算。「おかん、俺、友達おれへんから修学旅行いかへんよ」。こんな切ない会話をしている母と子に、さらなる貧困を強いるものとなりました。
舛添要一厚生労働相は、母子加算(月2万3千円)に代わり「就労促進費」(仕事をしていたら月1万円、職業訓練を受けていたら月5千円)などをつくったといいます。しかし、削られた額の方が大きいうえに、「就労促進費」は働いていない人はもらえません。
 病気などで働きたくても働けない母子家庭は3万世帯。生活保護を受けている母子家庭の3割を超えます。
病気などで働きたくても働けない母子家庭は3万世帯。生活保護を受けている母子家庭の3割を超えます。
私は「ぎりぎりの生活をしてきた人たちから母子加算まで削るような政治でいいのか。15兆円もの補正予算を組みながら、わずか200億円の母子加算の復活をしない。麻生内閣の経済対策は方向が根本的に間違っている」と怒りを込めて批判しました。
次いで、児童扶養手当(月約1万〜4万円)の対象が母子家庭のみで、父子家庭が一律に排除されている問題を質問。
小渕優子少子化担当相は「母子家庭であっても父子家庭であっても、苦労しながら低収入で仕事・子育てをしていることは変わらない。時代の変化を踏まえて検討していかなければならない」と見識ある答弁。
ところが、舛添厚労相の答弁がひどかった。「小渕大臣の発言は間違っている。母子家庭と父子家庭は違う。父子家庭は低収入ではない」と自分と同じ内閣の閣僚答弁を否定したのです。
そこで、父子家庭のうち就労収入が年300万円未満の割合はどのくらいか質問。厚労省担当官は37%になると答弁。そう、児童扶養手当の所得制限以下の父子家庭は少なくないのです。
 それでも、舛添厚労相が「母子家庭が困っているのは仕事、父子家庭が困っているのは家事」などというので、厚労省調査で父子家庭が「困っていること」の1位と2位を述べよと求めると、担当官は「1位が家計、2位が家事」と答弁。そう、父子家庭も「収入の低さ」にいちばん困っているのです。
それでも、舛添厚労相が「母子家庭が困っているのは仕事、父子家庭が困っているのは家事」などというので、厚労省調査で父子家庭が「困っていること」の1位と2位を述べよと求めると、担当官は「1位が家計、2位が家事」と答弁。そう、父子家庭も「収入の低さ」にいちばん困っているのです。
それには理由があります。離婚、死別などで父子家庭になったお父さんは、それまでの「仕事中心」の生活から、「子ども中心」の生活に切り替えなければならなくなります。保育所の送り迎えなどで「残業ができなくなった」「元の職場をやめなければならなくなった」という人も少なくありません。そうなれば収入は大幅にダウンします。
“わからずや”の舛添厚労相に、「同じひとり親家庭なのに、母子・父子で区別され支援が受けられない不公平は直ちに見直すべきだ」と強く求めました。きょうはここで時間切れ。
引き続き、母子家庭、父子家庭の支援と、すべての子どもの貧困をなくすために、みなさんとともにがんばりたいと思います。